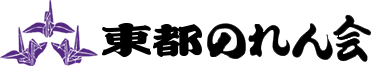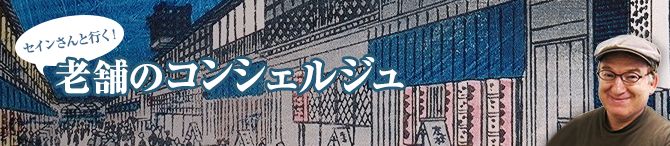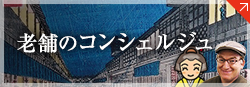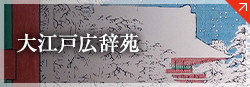秋、夜空を月が明るく照らすようになってきました。空気が澄んでいるのでしょうね。見上げると心が落ち着いて……お月見はヒーリング効果があるのかもしれませんね。
ところで、お月見に「団子」がつきものとされているのはなぜなんでしょう。一説には、中国のお月見の際に供えられる「月餅」が日本に渡って月見団子になったと聞きます。また、韓国のお月見ではソンピョンというお菓子が作られますが、これが原型という説もあるようです。
いずれにしても、ススキやお神酒などとともに備えられる真っ白なお団子は、清らかで、ほのぼのとしてやさしく、美しく、中国や韓国の伝統の食べ物とはちょっとイメージが違う、日本ならではの静けさに満ちているように思います。 |
 |
 |
さて、前置きが長くなりましたが、今日は向島の名物「言問団子」のご紹介です。こちらは3色。小豆餡、白餡、味噌餡の3種類で1セットです。
串に刺さないのが特徴で、これは「ゆっくり腰掛けて、くつろいで召し上がってください」とでもいった、この店のもてなし方から生まれたのでしょうね。店内でいただく場合は、都鳥が描かれた皿で供されます。
豆は北海道産の極上品、新粉は最高級のコシヒカリと素材を選び抜き、なめらかに仕上げられた団子は、口あたりも上品です。文人墨客に愛されたのもわかるような気がします。 |

店が立つ隅田川畔は、江戸時代には白魚が泳ぐ澄んだ川と河岸がつくる景色の美しさに文化人が集まり、風雅を楽しむ場所でした。当時のお月見は、中秋の名月「十五夜」だけでなく、十七夜以後を立待月(たてまちづき)、居待月、寝待月、更待月と呼んで、夜遅くなって昇ってくる月を楽しんだといいます。
それに合わせて言えば「言問団子」は十五夜以後のお月見に似合いの風情。おっとりとした表情が、この店の団子の真骨頂です。