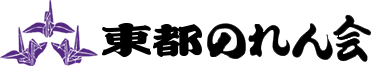こんにちは、東都のれん会です。
桜の花と入れ替わるように若葉が芽吹いて、都会も野山も新緑に染まる季節になってきました。“花より団子”派にとっては、新茶も待ち遠しいところですね。
そこで今月は、江戸後期の茶摘みの様子を描いた『狂歌茶器財集』から、とっておきの一枚をご紹介します。この時代に一大ブームを巻き起こした狂歌ですが、この本も口絵を廣重が描くという贅沢な一冊なのです。
絵の細かな部分に注目してみてください。すると、幟に「山」の字。摘んだ茶葉を入れる籠には「山本」。そして杭には「日本橋通二町目 山本嘉兵衛茶園」……。つまりここには山本嘉兵衛すなわち現在の山本山が所有する宇治の茶園が描かれているのです。
煎茶の原型は、京都・宇治の茶師・永谷宗円(永谷園の創業者の先祖)がつくり、山本嘉兵衛(山本山の創業者)が日本橋で売り出して世の中に広まりました。300年の時を超えて、今も江戸時代から続く店が当たり前のように東京の街にあることに驚かされますね
東都のれん会から、日々を豊かにする4月の話題をお届けします。

『狂歌茶器財集』、清流亭西江編、歌川廣重(初代), 歌川芳虎画,安政2年,山本山蔵