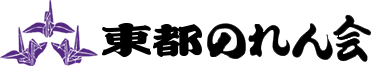毎年12月17~19の3日間は、浅草寺の羽子板市。この市のルーツは、江戸時代に成立した正月用品を商う「歳(とし)の市」にあります。
当時、江戸では各所で定期市が開かれていましたが、なかでも賑わったのが年末の「歳の市」。江戸中期まで、歳の市がたつのは浅草に限られ、納めの観音詣にあたる師走の17・18日に開かれていました。小屋掛けの店が浅草寺境内から蔵前、浅草橋、上野山下あたりまで軒を並べたといいますから、大きな規模だったようです。
ところが、この市に買い物に出かけたのは、なんと男だけでした。武家や大店の主人が家来や奉公人を引き連れて繰り出し、毎年決まった店で買い物をし、帰りには料理屋に寄って威勢をつけて帰る――それが江戸っ子の「粋」だったのです。
江戸時代も後期になると、浅草の市のあと神田明神や深川八幡などにも歳の市がたつようになり、女性も出かけるようになりました。しかし、次第に一般の店でもお正月用品を売るようになると、歳の市はすたれ、浅草の市も江戸時代中期から庶民の間に流行し始めた羽子板を売る市へと変わっていきました。今に伝わる「羽子板市」の始まりです。
羽子板のルーツをたどると、14世紀の中国に始まった、大きな羽根を足で蹴り上げあう子どもの遊びにたどり着くようです。
板でつく羽根つきは、15世紀初頭に日本に渡ってきてからのもので、まずは宮中や公家の間で、お正月の遊びとして楽しまれました。永享4年(1432)に書かれた宮様の日記によると、羽根つきのことを「こきの子勝負」と書いています。当時は羽根のことを「こぎのこ」、羽子板は「こぎのこ」と呼んでいたんですね。これより100年ほどあとの文献には、年末に足利将軍家が宮中へ羽子板を献上したことなども書かれています。どうやら、このあたりから、羽子板は、遊び道具とは別に、ご祝儀の品という色合いも濃くなっていきます。
なかでも、江戸時代に京都で作られていた「左義長羽子板」は、贈答品として、また姫君の輿入れにも使われたことから、胡粉を盛り上げ、金泥などで彩色した美麗な羽子板でした。縁起物としての羽子板は、江戸文化の発展とともに、いよいよ豪華になっていったのです。
最新記事
This post is also available in: 英語